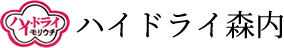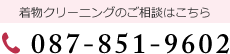着物の雑学
Trivia着物には、衣料品としての実用品価値よりも、美術工芸品としての付加価値をつけた品物が多くあります。
刺繍、絞り、金銀彩、螺鈿(らでん)、その他・・・。
単一ではなく、組み合わせた手法もあり、多種多様です。このため、お手入れ、保管においても格段の注意が必要です。
しみに気づかず放置したり、反対にあわてて間違った手当をしてしまうと、取り返しのつかないことになる場合があります。
しかし、着物を知りつくしたしみぬきの技法・修復の技法を駆使すれば、お召しになっていただける状態に戻すことができる場合が多くあります。
お客様にお喜びいただけることが、なによりの励みです。
どうかあきらめずに、ぜひご相談いただきますよう、お願いいたします。
絹とは?
古代中国、今から3,000年以上前に、養蚕(カイコを育てまゆを取る)は始まったと言われています。
天然繊維唯一の長織維で、動物性たんぱく繊維であり、独特の光沢を持っています。これは、絹の三角断面構造による、反射吸収干渉でプリズム効果によるものと言われています。
軽く、空気を含む優れた吸湿性と染色性を持ち、衣料品をはじめ、多種多様な用途があります。
耐熱湿度も、天然繊維のなかでは高く、弱点としては、吸収性が高い分、湿じゅん状態での摩擦に弱く、スレ(毛羽立ち)を起こしやすいことです。
紫外線を吸収して変質しやすいので、直射日光、紫外線をさけて保管することが必要です。

絹を生み出すカイコとは?
カイコは蝶や蛾と同じ昆虫で、蚕の字をあて、糸を吐きマユをつくる昆虫(絹糸昆虫)全体を指します。
カイコの品種は約600種と言われており、養蚕として産業的に利用されている種は人工交配されてものです。
原種は大切な遺伝子資源として大切に保管されており、時代にあった性能を持つ絹を生産するために、改良され生み出されたサラブレットなのです。
デリケートなカイコを育てるためには、無農薬で良質の桑の木を育てることから始まり、大変な人手が求められます。
以前はあまりに過酷な労働条件のために、後継者不足に悩まされていました。
高タンパクの桑の葉を食べ、4回の脱皮を経て、カイコは自分の消化したタンパク質の60~70%を体内に貯め込み、これを原料に糸を吐きマユを作ります。
2~3日かけて1.500mもの糸を吐き続けマユを完成すると、サナギになり、眠りにつきますが、そこで命を終えることになります。
成虫になりマユを食い破ってしまうと、商品価値がなくなってしまうからです。マユ糸を5~10本繰り合わせて、絹糸にします。
絹・・・それは小さな命がこもった自然の贈り物なのです。どうか、大切に愛情をもって絹、和服とお付き合いください。
呉服の由来は?
呉服の語源は諸説ありますが、中国の三国時代、(魏、呉、蜀)に呉から、織物や着物の縫製方法が日本に伝わったことにあるとされています。
胸元で衿合わせする形式の衣服が伝えられ、日本での衣服の祖になったという説があります。
左前と右前の混用について
着物の場合は、男女とも右前です。右衿を先に合わせて、左衿を重ねます。
これは奈良時代の法令によって統一されました。
洋服の場合は男用が右前、女用が左前です。
【礼装】振袖と留袖
振袖というのは、もともと身八つ口をあけて振りをつけ、仕立てた着物で袖丈を長くとった着物の総称です。
未婚女性の第一礼装です。
留袖とは、振袖のたもとを短く切った(切ることを留めると言った)袖丈をつめた詰袖とも言われました。
既婚女性の第一礼装です。